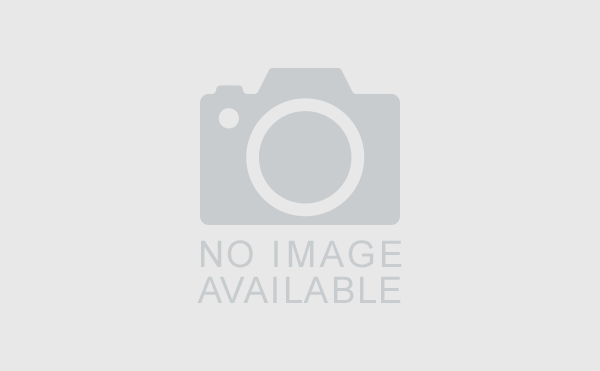相続回復請求権の消滅時効の完成前であっても、取得時効や債権の消滅時効の成立を妨げるものではないとして裁判例(最判R6.3.19)
被相続人Aの死亡後、養子であり唯一の法定相続人Yは、Aの遺産をすべて相続しました。しかしその後、Aが生前に「遺産をY、X1、X2に等分する」とする自筆証書遺言を作成していたことが明らかとなり、XらはYに対して、この遺言に基づいてAの相続財産の一部を請求しました。
これに対してYは、まず主位的に「本件遺言は無効である」との確認を求め、仮に有効とされた場合に備えて、予備的に「不動産および預貯金等については、取得時効や債権の消滅時効が成立しているため、Xらに請求権はない」と主張しました。XらはYの予備的主張に対して、相続回復請求権の消滅時効が完成しておらず、真正相続人が相続回復請求をすることができる間は、民法162条の取得時効によって所有権を取得することはできないとして争いました。
遺言は有効と認定されていますので、以下、Yの予備的主張に関してのみ述べます。
第一審も控訴審も、相続回復請求権の消滅時効の完成前であっても、取得時効や債権の消滅時効の成立を妨げるものではないとして、Yの予備的主張を認め、Xらの請求を棄却しました。
本判決も、「民法884条所定の相続回復請求権の消滅時効と同法162条所定の所有権の取得時効とは要件及び効果を異にする別個の制度であって、特別法と一般法の関係にあるとは解されない。また、民法その他の法令において、相続回復請求の相手方である表見相続人が、上記消滅時効が完成する前に、相続回復請求権を有する真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられる旨を定めた規定は存しない。
そして、民法884条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある・・・ところ、上記表見相続人が同法162条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは、上記の趣旨に整合しないものというべきである。
以上によれば、上記表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当である。このことは、包括受遺者が相続回復請求権を有する場合であっても異なるものではない。」として、やはりYの予備的主張を認めました。
この判決から導き出される実務上のポイントは次のとおりです。
- 表見相続人(法定相続人でないが相続人のようにふるまった者)であっても、一定の占有期間があれば、真正相続人の回復請求権の時効完成前でも、取得時効を主張して所有権を取得できる。
- 相続開始後に遺言が発見された場合でも、早期に財産を占有・管理し、時効期間が経過すれば、相続財産を確定的に取得しうる。
本件は、「相続回復請求権が消滅するまで取得時効は主張できない」とする見解を排し、取得時効の制度趣旨(長期の事実状態の安定)を優先しました。こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。