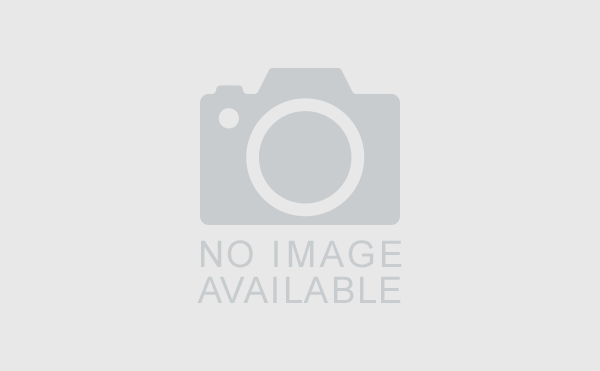特別寄与料と遺留分侵害額請求の関係について(最決R5.10.26)
本件は、被相続人Aの死亡後、その子であるBの妻Xが、Bの兄弟であるYに対し、Aに対して行った療養看護等の貢献を理由に、民法1050条に基づいて特別寄与料の支払を求めたものです。
争点は、被相続人が遺言によって自己の財産全部をXの夫であるBに相続させる旨を明記していたことから、他の相続人であるYには「相続分がない」こととなった状況であったものの、YはBに対して遺留分侵害額請求をしていたことから、Yに対して特別寄与料を請求できるかという点がでした。
第一審、控訴審とも、遺言で相続分が0とされた相続人には、特別寄与料の負担義務がないとして、Xの請求を棄却しました。
本決定も、「民法1050条5項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解される。このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。そうすると、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。」として、Xの請求を認めませんでした。
このように、最高裁は、民法1050条5項の解釈について、「相続分がない」とされた相続人が遺留分侵害額請求をした場合であっても、なお特別寄与料を負担する義務はないと明確に判示しました。
この判例から得られる実務上のポイントは、以下の通りです。
- 特別寄与料の請求において、請求相手(相続人)の「相続分」は、遺言で指定された「指定相続分」によって決まり、それが「0」であれば負担義務は生じない。
- 仮にその相続人が遺留分侵害額請求をしたとしても、それによって特別寄与料の負担義務が生じることはない。
本件は、民法1050条の制度趣旨である「相続人間の公平」と「紛争の複雑化防止」とのバランスにおいて、相続分を採用することを明確にしました。こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。
さらに詳しく知りたい!→特別寄与分制度(民法1050条)について詳しく知りたい方は、こちらのサイトをご参照ください。