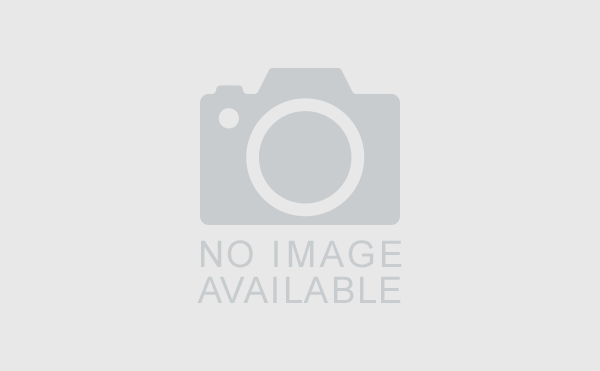共同相続人の一人による被相続人の預金払い戻しが不当利得とされた事例(東京地判R3.9.28)
本件(東京地判R3.9.28)は、共同相続人間における生前・死後の預金出金に関して不当利得返還請求が争われた事案です。XとYは被相続人の子であり、共同相続人はこの二人のみでした。Xは、Yが被相続人の預金口座から無断で出金したことについて、不法行為による損害賠償とは別に、不当利得返還請求権を相続したとして、金員の返還を求めました。
Xは、既に別訴で生前の出金に関する損害賠償請求を提起し、そのうち法定相続分に相当する約4700万円の支払いを受けていました。しかし今回の訴訟では、XはYに対して、具体的相続分に基づいて算出された金額との差額分として、さらに約2100万円の不当利得返還を求めました。
また、被相続人の死後における出金(本件死後出金)についても、法律上の原因がなく、悪意の受益者であるとして、手数料を入れて260万円の全額の返還を求めました。
まず、生前出金に関する判断について、裁判所は「不当利得返還請求権は、相続開始と同時に、法定相続分により当然に分割されるものであり、この法定相続分に相当する金銭については、既にYからXに支払がなされているから、…既払額を超える額の支払を求めるXの請求には理由がない。」と説示しました。
つまり、被相続人が有していた不当利得返還請求は、法定相続分(この場合は2分の1)によって当然に分割されるものとされました。
次に、死後出金について、裁判所は最高裁平成28年大法廷決定(預金債権は可分債権にあたらず、当然分割されない)を前提としつつ、「本件口座は、XとYにおいて各2分の1の潜在的な持分割合による準共有状態にあった…Yによる本件死後出金は、その2分の1に相当する金額については、Xに対する準共有持分権の侵害となり、不当利得を構成し得る。」
また、Yが出金時点で法定相続分を超えて出金していたことを認識していたことから、民法704条に基づく悪意の受益者としての責任も肯定しました。
本判決から、次のような実務上のポイントが導かれます。
- 相続において、金銭債権(不当利得返還請求権を含む)は、法定相続分に基づいて当然に分割される(但し、ここは異論もあります)。
- 被相続人死亡後の預金出金については、預金債権の性質上、共同相続人の準共有財産とされ、持分を超える出金は不当利得となる。
- 法定相続分を超える出金を行った相続人が、その超過について法律上の原因がないことを認識していた場合、民法704条の「悪意の受益者」として利息付きの返還義務を負う。
遺産分割調停で過去の出金等が遺産に含まれていない場合であっても、不当利得返還請求の放棄にあたるとまではいえないと考えられます。遺産分割にあたっては、過去の出金を明らかにしたうえで、過去の出金が既分割か否か、放棄か否かを明示しておくことが、紛争防止には重要です。
また、被相続人名義の預金は、相続開始時点では準共有状態と解されるため、法定相続分に基づかない出金(他の相続人の承諾なく行ったもの)は、準共有持分の侵害として問題となる可能性があります。注意が必要です。
こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。
相続財産の範囲について確認したい方はこちらをご参照ください。