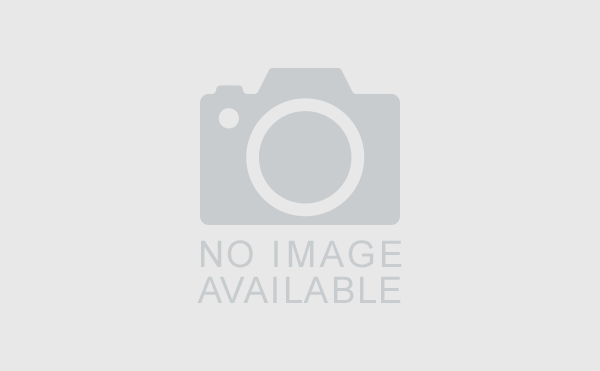共同相続人の一人が被相続人の生前被相続人の預金を払戻した金員につき、他の相続人からの寄託金返還請求が認められた事例(東京高判R4.4.28)
本件(東京高判R4.4.28)は、在日韓国人であるGの預金を、その子であるXがGの生前に払い戻し、自らの口座に移した行為について、他の相続人Yらが不法行為および不当利得に基づく返還請求を行った事案です。争点は、Xに払戻権限があったかどうか、そして返還義務の有無にありました(なお、Xは預金の引き出しに応じた銀行に対しても訴訟提起を行っていますが、その点は省略致します)。
第一審(東京地判R3.6.30)は、Xの行為を無権限の払戻としましたが、本判決は、「XがGから預金の払戻権限を与えられていたと認めるのが相当である。したがって、Xの行為は正当な権限に基づくものであり、不法行為又は不当利得に基づく請求は理由がない。」としました。
その一方で、本判決は、Xが預金を引き出した行為はGの承諾に基づくものとはいえ、GからXに対し金銭を「寄託」したと認め、「GがXに対し、当該金員を軽々に贈与することは考え難いこと、またX自身が返還の意思を表明していたこと等から、XはGから寄託を受けたものと解するのが相当であり、寄託金返還請求は認められる。」
つまり、控訴審では、主位的な不法行為・不当利得請求は否定されつつも、寄託金返還請求という予備的請求が認容されました。
この裁判例から得られる実務上のポイントは以下のとおりです。
- 被相続人の生前の預金払戻については、形式的な無権限に見えても、事実関係に即して払戻の「正当性」(黙示の権限付与等)が認められる場合がある。
- 不法行為や不当利得が成立しなくても、寄託関係が成立していれば、寄託金返還請求が成立し得る。
相続人が被相続人の高齢や判断能力の低下を背景に預金の払戻をした場合でも、その正当性や法律関係は一律には扱えず、事実関係に大きく依存します。被相続人の委託に基づき預金を引き出す場合には、事後的に紛争が生じないように、何らかの証拠を残しておくことが肝要です。
また、単なる寄託でなく贈与である場合には、明確な証拠を残しておくことが肝要です。
こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。
相続財産の範囲について確認したい方はこちらをご参照ください。